ほくりく先導型研究開発の国際連携拠点形成【広域化プログラム】
| プログラムリーダー | 金沢工業大学 客員教授 橋本 勲 |
| 国内参画機関 | 金沢工業大学、金沢大学、北海道大学、東京大学、京都大学、大阪大学、広島大学、九州大学、札幌医科大学、青森県立保健大学、大阪市立大学、慶応大学、首都大学東京、近畿大学、国立岡崎生理学研究所、国立神経医療センター、独立行政法人国立病院機構 西新潟病院、財団法人広南会広南病院、独立行政法人産業技術総合研究所、医療法人 藤田神経内科クリニック、NICT神戸研究所、株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)、日本光電株式会社、横河電機株式会社 |
| 海外参画機関 | 国立物理学・工学研究所(PTB)(ベルリン)、イルメナウ工科大学、ハイデルベルク大学(ドイツ)、ヘルシンキ工科大学(フィンランド)、ウィスコンシン大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、テキサス大学医学部ヒューストン校、ニューメキシコ大学 ワシントン大学(米国)、トロント小児病院(カナダ)、国立陽明大学医学院、長庚紀念医院(台湾)、国立ソウル大学(韓国) |
また、MEGのハードウェア、ソフトウェアについて国際的なリーダーシップと優位性を確保し、国際研究開発拠点を形成するために、国際的な共同研究を行います。さらにヒト脳機能の基礎研究ならびに臨床応用に関する研究・情報交換を行うと共に、国際シンポジウムを開催して、MEGの国際的な標準化に向けて北陸地域における研究情報を世界へ発信します。
具体的には以下の問題点を解決します。
(1)MEGを評価する標準ファントムが存在しないため、 機種間でデータの互換性がない。
(2)解析ソフトウェアの信頼性が確立されていない。
(3)刺激法と(4)診断プロトコルが研究者によりまちまちであるためにデータの比較、共有ができない。
このような現状を打開し、研究を発展させるにはMEG関連の広い領域での標準化を推進する必要があり、全体会議を設置しました。上記の問題点を解決するために標準化の望ましい関連領域として、
(1)ハードウェア(ファントム)
(2)解析ソフトウェア、
(3)刺激法(パラダイム)
(4)診断プロトコル
を挙げることができます。4つの分科会を設置して、上記領域の標準化を個別に推進します。
各研究組織による共同研究成果に基づいて世界に向けてMEG国際標準化の提言を行い、公の学会(日本臨床神経生理学会、日本生体磁気学会、国際生体磁気学会、国際臨床脳磁図学会)に提案して、ガイドライン化をサポートし、国際的にオーソライズしていくことが最終目標です。
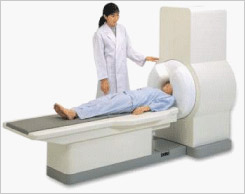 |